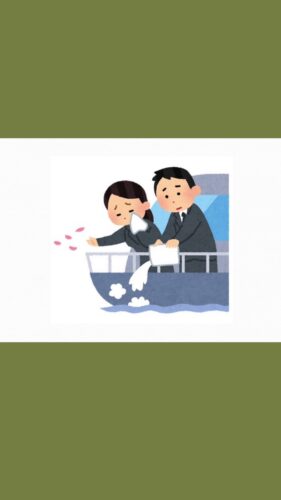秋のお彼岸とは?今だから知りたい由来と過ごし方
投稿日:2025年09月27日
・
こんにちは。
江藤です。
・
今年の秋のお彼岸も終わりましたね。
お墓参りに行けた方も、忙しくて足を運べなかった方も、
それぞれの形でご先祖様を想った時間があったのではないでしょうか?
改めて「秋のお彼岸とは何か」を振り返ってみたいと思います。
秋になるとニュースやカレンダーでよく耳にする「お彼岸」。
でも、改めて聞かれると「なんとなくお墓参りする時期」というイメージだけで、
詳しくは知らない人も多いかもしれません。
お彼岸とは
お彼岸とは、春と秋の年2回あり、春分の日・秋分の日を中心とした
前後3日、合計7日間を指します。つまり秋のお彼岸は、秋分の日をはさむ7日間のことです。
お彼岸の由来とは
「彼岸」という言葉は仏教からきています。サンスクリット語の「パーラミター(到彼岸)」を漢訳したもので、「迷いや苦しみの世界(此岸・しがん)」から「悟りの世界(彼岸)」へ至ることを意味します。ちょうど昼と夜の長さがほぼ同じになる春分・秋分は、バランスが取れた特別な日とされ、ご先祖様を敬う風習と結びついて日本独自の「お彼岸」の習慣になったといわれています。

秋のお彼岸とお墓参り
秋のお彼岸は、先祖供養のためにお墓参りをする大切な時期です。
墓地を清掃したり、お花やおはぎを供えたりして、ご先祖様へ感謝を伝えます。
おはぎを供える風習は、秋に咲く萩の花にちなんで「おはぎ」と呼ばれるようになったとも言われています。
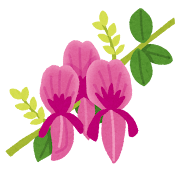
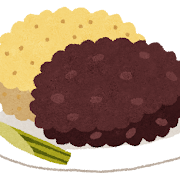
まとめ
秋のお彼岸は、昼と夜が同じ長さになる秋分の日を中心に、ご先祖様を想い、感謝を伝える大切な期間です。由来を知ると、ただの習慣ではなく「心のバランスを整える行事」として感じられるはず。忙しい毎日の中でも、お墓参りや心の中で手を合わせるひとときが、私たち自身の心を豊かにしてくれるでしょう。
.