お盆のお墓参りマナーと、お参りできないときの気持ちの届け方
投稿日:2025年08月17日
こんにちは☀
江藤です。
お盆も終わり、少しほっと一息つかれている頃かと思います。
皆さまはこの夏、お墓参りに行かれましたか?
お盆のお墓参りの意味
お盆は、ご先祖さまや亡くなった方の霊を迎えて供養する大切な行事です。
毎年この時期になると、多くの方が帰省してお墓参りをされます。けれども、「マナーがよく分からない」「遠方で行けなかった」というお声もよく聞きます。今回は、お盆のお墓参りの基本と、行けないときにできる気持ちの届け方についてお伝えします。
基本的なお墓参りの流れ
お墓参りの基本的な流れはとてもシンプルです。
まずは墓地に到着したら軽く一礼をし、掃除から始めます。
雑草を抜いたり、墓石を布で拭いたりと、きれいに整えることが何よりの供養です。
その後、お花やお供え物を飾り、お線香をあげます。手を合わせるときは、堅苦しく考えず「いつも見守ってくれてありがとうございます」と自分の言葉で伝えることが大切です。
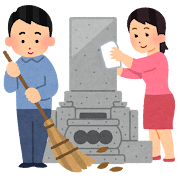
またお墓参りの時に注意したいのは熱中症です。
➀帽子や日傘で日差しを避ける
➁水分や冷やしタオルを持ち歩く
③できるだけ朝や夕方の涼しい時間帯を選ぶ
そして熱を持った墓石にも注意が必要です。

気持ちを伝えることが大切
ただ、近年はライフスタイルの変化もあり「仕事で休めない」「実家が遠くて帰れない」という方も増えています。そんなときでも気持ちを届ける方法はあります。たとえば、自宅でご先祖さまに手を合わせる、仏壇にお花を飾る、写経やお香を焚くといった形でも十分に心は伝わります。

これからの供養の形を考えるきっかけに
大切なのは「必ず現地に行かなければ供養にならない」ということではありません。
お盆という特別な時期に、ほんのひとときでもご先祖さまや大切な人を思い出すこと。
それ自体が立派な供養の時間になるのだと思います。
まとめ
お盆をきっかけに、お墓のことや供養の形について家族で話し合う方も増えています。
従来のお墓参りに加えて、樹木葬や永代供養といった新しい選択肢も広がっています。供養の仕方は一つではなく、それぞれの暮らしに合った方法を選ぶ時代です。今年のお盆を振り返りながら、ご先祖さまとのつながりをどう守っていくか、一度考えてみてはいかがでしょうか。








